脊 髄 損 傷
ж 脊髄損傷後の変化 ж
脊髄が傷つくと、断裂,鈍的損傷,圧迫(骨折・骨の腫れ・出血などによる)が起こる事がある。
脊髄は組織化されている為、脊髄が損傷すると常に損傷部位より下方の神経機能が失われる。
例えば背中の真中の脊髄が酷く損傷すると、腕は正常に動くが脚は麻痺する。
侵された領域の感覚と筋肉の運動機能が失われる。
脳の支配を受けていない反射はそのまま残るが、損傷部位より下方の部位では反射が増大する事もある。
例えば膝蓋腱反射では、膝のすぐ下を小型のハンマーで軽く叩くと、
正常であれば下肢が上方に跳ねるが、脊髄が損傷していると脚が攣縮する結果、痙性麻痺の症状が現れる。
これは膝蓋腱反射をコントロールする筋肉が緊張して硬直し、
断続的に収縮して脚の引き攣りを起こす為である。
麻痺と感覚消失が身体の一部や全身に起き、それが一時的に現れたり永久に続いたりする。
外傷などにより脊髄が断裂したり脊髄の神経路が破壊されると、
機能は永久に失われる。
一方鈍い衝撃による脊髄損傷では、消失は数日から数週間あるいは数ヶ月症状が続く一時的なものになる。
麻痺が完全ではなく、損傷後1週間以内に運動と感覚の機能が戻ってくれば、
回復の見込みは大きくなる。
6ヶ月以内に機能が回復しない場合は、一生機能が戻らない可能性がある。
脊髄損傷によって脱力や麻痺を起こした場合、褥瘡(床ずれ)尿路感染症,肺炎を起こすリスクが高くなる。
ж 初期の運動麻痺 ж
中枢神経である脊髄が損傷されると、脊髄の機能は損傷部位以下が一時的にすべて停止する。
運動や知覚,反射といった身体の基本的な機能が失われるこの時期を
脊髄ショック期と呼ぶ。
しかし、この時期に少しでも肛門の周囲の感覚があったり、
足の第1趾を少しでも動かす事が出来る様なら、
脊髄は必ずしも完全には損傷されていないかもしれない。
脊髄ショック期はおよそ24時間から3週間位続く、
やがて損傷された脊髄の部位から下位の、脊髄固有の反射から復活し始め、脊髄ショック期は終わる。
脊髄固有の反射には「 球海綿体反射 」と「 肛門反射 」がある。
損傷の後にくる麻痺にも、損傷の種類によって幾つかの種類がある。
例えば頸髄(首の部分)を損傷すれば四肢麻痺が起こり、
胸髄(背骨の上方)より下の部分を損傷すれば対麻痺となる。
この様に脊髄のどの部分(髄節)が損傷されたかによって
どの筋肉が麻痺を起こすかが決まってくるので、
寝返りや起き上がり,座った姿勢を保つ,移動や乗り移り動作,食事やトイレ,身だしなみといった
日常生活動作〈 ADL 〉等が様々に障害されてくる。
肋間筋,腹筋の麻痺の為、胸式呼吸が妨げられる。
C4以上では横隔膜麻痺が生じ、呼吸が重篤に障害される。
ж 初期の知覚麻痺 ж
【 知覚の種類 】
触覚・痛覚・温度覚・位置覚などがある。
触覚は、毛や筆を使って調べ、痛覚は、ピンで軽く押して調べ、温度覚は、冷水や温水などで調べる。
また位置覚は、足の第1趾を曲げてその位置を答えてもらう事で調べる。
【 知覚麻痺の程度 】
知覚がなくなっているか? 鈍くなっているか? 逆に過敏になっているか? を調べる。
【 知覚麻痺のある範囲 】
〔 デルマトーム 〕
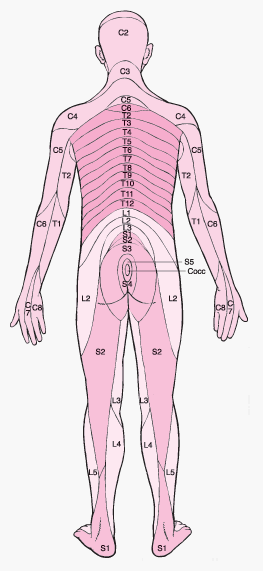
皮膚には脊髄の各髄節毎に対応したある範囲があり、その地図も作られている。
知覚障害のある範囲もその地図に従って調べる。
四肢麻痺や対麻痺では、完全損傷の場合には知覚が回復する可能性は残念ながら低いといえる。
しかし、最初から第5仙髄神経節に少しでも感覚が残っている様ならば、
脊髄が完全に断たれた事による麻痺(完全横断性麻痺)ではなく、
不完全麻痺である可能性が高く
(sacral sparingといい仙髄節神経が残存し、完全脊髄損傷でない事を示す)
リハビリテーションによって運動が回復してくる可能性もある。
ж 自律神経機能障害 ж
【 血管運動機能障害 】
脊髄での自律神経機能障害は、[ 延髄-脊髄血管運動路]が遮断されたり、
脊髄血管運動中枢が壊れたりする事によって起こる。
麻痺した部分の血管は張りを失って拡張し、体温も上がり、皮下静脈も拡張する。
【 起立性低血圧 】
所謂「 たちくらみ 」である。
急に起き上がったり、長時間座っていると気分が悪くなったり、動悸がしたり、冷や汗をかいたり、
時には目の前が真っ白になったりする。
頸髄損傷では一般に最高血圧が90,最低血圧が60くらいの低い人が多い。
【 体温調節障害(発汗障害)】
頸髄損傷や高位の胸髄損傷の場合は発汗障害があり、
汗の蒸発による体温冷却作用が起こらず、体温が体内に蓄積されて熱っぽくなり、
体温が上がり、めまいがしたり気分がすぐれない、酷い時には意識が朦朧となる事がある(うつ熱状態)
夏期に直射日光に当たったり,気温の高い場所に長くいたりすると起こる、
又、室温が25~26℃以上になると発生する。
【 消化管機能障害 】
急性期や慢性期には消化管の運動機能が障害される事がよくある。
症状が重い場合には麻痺性イレウスになり、危険である。
その為に、規則正しい食事やトイレの習慣をつける必要がある。
便秘ぎみの場合、沢山の水を飲んだり、繊維性の食品を沢山食べたり、
場合によっては緩下剤や消化管運動促進剤を服用する事もある。
【 自律神経過反射 】
頸髄損傷,高位胸髄損傷の場合には、
異常な発汗や頭痛,血圧の上昇,徐脈,顔面紅潮などが現れる。
これは尿や便が充満した結果、自律神経が過敏に反応した結果である。
その都度、医師に相談し、適切な処置をとって
原因を取り除く必要がある。
ж 排尿機能障害 ж
【 損傷直後の排尿障害 】
脊髄ショック期には排尿神経が麻痺し、
膀胱が収縮せず、尿が出なくなる(「 尿閉 」)→『 神経因性膀胱 』
外尿道括約筋も開かない。
この状態を放置すると、膀胱には1,000ml以上の尿が溜まり、
この状態が続くと尿毒症になる事がある。
その為に、カテーテルを膀胱に留置したり、数時間毎に導尿する。
ж 排便機能障害 ж
【 急性期の排便障害 】
急性期には全身がショック状態に陥っており、
腸管運動も低下し、便も硬くなり、便秘になる。
麻痺性イレウスになる事は比較的少なく、初めから水分と軽い食事を摂る事も可能である。
腸管運動が緩慢ならば手術後の腸管麻痺を扱う様に、
胃管を入れ、腸管麻痺が改善したら胃管を抜去し、
次に軽い食事から普通食に切り替えていく方法もある。
その間、必要に応じ『 摘便 』を行う。
その後は、水様便や泥状便の状態になる事もある。